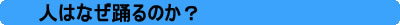

人はなぜ踊るのか、踊りたい気分になるのか。
辞典(大辞林・三省堂)には『「踊る」とは、「音楽などに合わせてからだを動かす」、「舞踊を演ずる」、また「躍る」と同じく「飛び跳ねる」、「跳ね上がる」の意味を持ち、「喜びや期待などで鼓動が激しくなる」、「わくわくする」、「激しく揺れ動く」を示す。
「踊る」が、本来、飛び跳ねる意であるのに対し、「舞う」は地をするように旋回する意を本義とする。』とあります。
ラテン音楽が流れると中南米の人は自然にステップを踏んでいたり、幼児は軽快でテンポの良い曲を聞いた時に全身でリズムを取ったりします。
踊りに音楽は欠かせませんが、楽しい気分や鼓動を高める状態になると、DNAの持つ情報により人は生理的に踊らされていると思えてきます。
また、各地にある伝統的な祭りの舞い「神楽」は、踊りを通じて神仏に祈り、来臨や神託を願う、つまり神との交信を信じていたことになります。
鎌倉時代に広まった踊念仏も、布教活動に踊りの神懸り的なイメージを活用したかもしれません。
日本では、この踊念仏の広まりから、盆踊りや出雲阿国が創始した歌舞伎踊りの芸能に発展したと言われています。
潜在的にも娯楽的にも、昔から踊りは人間に受け入れられ易く、とても近くにあったのです。
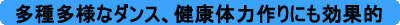
さて、現代の日本ではどうでしょう。
皆さんの家族や友人など身近な知り合いにダンスをする人はいますか?
日本人の恥ずかしがり家な気質が災いして、ダンス実践者はあまり多くありません。
観賞するのは良くても、踊るのは敬遠されがちです。
しかし、社交ダンスをはじめ、バレエ、ヒップホップ、フラメンコ、サルサにバリ舞踊など‥
海外の情報が手軽に入手できるので、その気になれば多種多様なダンスを体験できます。
つまり、多種多様なダンスの中で、音楽のスピード、動きの難易度、自分の好みに合わせた振り付けの踊りを選択することができるのです。
ダンスを効果的な運動として行うためには、自分の体力にあった強度で継続的に行うことが必要です。
至適強度はスピードや難易度で、継続性は楽しさで選択することができます。
また、ダンスのように芸術性を求めないエアロビックダンスやリズム体操は、健康維持や体力づくりのエクササイズとして適しています。
本格的にダンス入門する前の腕試しには、お手頃です。
さあ、あなたの運動の一手段として、ダンスを選択肢に加えてみてください。

