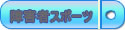選手が車椅子に乗り競技する以外は一般のバスケットボールとほぼ同じルールで行われる。
コートの広さ、バスケットの高さ、試合時間(1ピリオド10分を4ピリオド、計40分)はFIBAの規則と同じであり、フリースローで1得点、フィールドゴールは2得点あるいは3得点であることも同様である。
ファウルやヴァイオレーションのルールもほぼ同等となっている。唯一異なる点は、ダブルドリブルに相当するルールがない。
一回のドリブルに付き、2回以内のタイヤ操作が許されており、3回以上タイヤをこぐと、トラベリングとなる。
一度にコート上でプレーできる選手に関してはクラス分けによる一定の制限が設けられている。
これは選手が持つ障害を重度に応じて分類したもので、障害が最も軽度ならば4.5、重度ならば1.0のクラスとなる。
コート上の5人の選手のクラスは合計14.0を超えてはならない。
この制度は、重度の障害を持つ選手が競技への参加を妨げられないようにすることを狙いとしている。
クラスの目安として
1.0 - 腹筋・背筋の機能が無く、座位バランスが著しく悪い。
2.0 - 腹筋・背筋の機能が残っているため、わずかに前傾姿勢などがとれる。
3.0 - 下肢に筋力の残存があり、すばやく上体移動ができる。
4.0 - 主に切断など。体幹の側屈運動ができる。
それぞれのクラスで上位の運動能力のある選手には0.5ポイント加算される(最大4.5)。 人工関節などの軽度障害者にも参加資格が与えられている。
また海外などでは、健常者もクラス5.0として参加が許されている地域もあり、多くの人に門戸を開いている。
上半身で車椅子を動かし、ボールも操るため、選手の上半身は非常に発達している。
接触や転倒も頻繁に起こり、焦げたような匂いがするほどである。
片輪を浮かすティルティングやピック&ロールによる華麗なプレーなど通常のバスケットボールではみられない面白さがある。

バスケット用の車椅子の特徴として、タイヤが八の字になっており、すばやいターンが出来る。そして転倒防止用に後方にも小さな車輪がある。
一台25~40万円ほどで、高さなどが調節が出来るものと、選手それぞれにあわせた固定用とがある。
椅子の高さはシートの位置が最大53cmと決められている。

ピック・アンド・ロール
健常者バスケットでも頻繁に使われるプレイ。相手選手にスクリーンをかけて、味方選手がフリーになる状態を作り出す。
車椅子バスケでは通常のバスケットボールに比べ2次元方向の動きが重要であり、ディフェンダーをスクリーンにかけると数的有利が生まれるためとても有効である。
車椅子バスケにおいて基本となるプレイである。